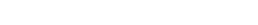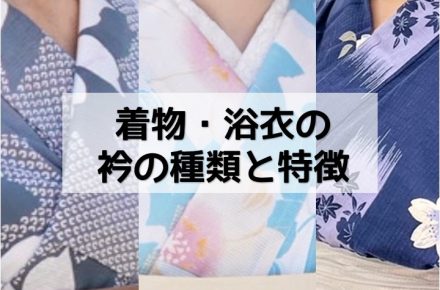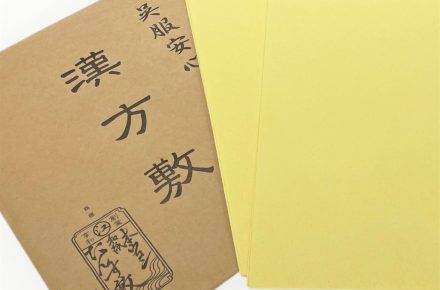草履を調整して足元を楽に過ごそう|台のベストサイズと鼻緒のすげ直しについて

こんにちは、すずのき編集部です。
店舗でよくあるご質問の中に、草履に関する内容が多くあります。
特に多いのがサイズの選び方とTPOについて。
草履を履くと足が痛くなるから、大きめを用意したら今度は歩きにくくて足が疲れてしまう……なんてご相談もあります。
今回の記事では、そういった草履に関するお悩みのうちの「サイズの選び方」を中心に解決していきたいと思います。
まずは、草履の台のサイズについてです。
草履の台の理想サイズ
草履の台のサイズは、洋靴のように「ぴったりフィット」ではなく、少し小さめに履くのが粋とされます。
基本の目安
- 草履のかかとから5mm〜1cmほど足が出るサイズがちょうど良いとされています。
- 長すぎる → 歩きにくく、見た目も重たくなる
- 短すぎる → 足がはみ出しすぎて不格好
足とのバランス
- 幅:足の横幅が台からはみ出しすぎないことが大事。少し出る程度なら問題ありません。
- 長さ:洋靴で23.5cmを履く人なら、草履は23.0cm程度を選ぶのが目安。
TPOによる違い
- フォーマル用(礼装・振袖など)
→ きっちり感を大事にするので、かかとの出具合は控えめ(5mm程度)。
- カジュアル用(小紋・浴衣など)
→ 少し出して軽やかに見せる(1cm程度)。
ちなみに、草履は鼻緒の調整で履き心地が大きく変わります。サイズだけでなく、購入時に必ず鼻緒を足に合わせて調整してもらうことが大切です。
草履の鼻緒の調整は、痛みを防ぎ快適に履くためにとても大事です。基本的には職人さんが「すげ直し」で調整してくれるのが一番確実ですが、自分でもできる軽い調整もあります。
自分でできる鼻緒の調整方法
鼻緒を手で揉む
- 鼻緒の布や芯を 手でやさしく揉んでほぐす。
- 前坪(指の股に当たる部分)を柔らかくすると痛みが減ります。
鼻緒を揺らす
- 鼻緒を持って 前後左右に軽く動かすと、少しゆとりが出ます。
- 特に甲がきついときに効果的。
鼻緒に指を入れて広げる
- 草履を履く前に、手の指を鼻緒に差し込んで軽く広げておく。
- 甲や足幅が楽になります。
職人さんに調整(すげ直し)をしてもらう必要があるのは、前坪(指の股部分)をきつめたり、ゆるめたりする場合や、甲の当たり具合を広げたり狭めたりする場合などです。
幅広・幅狭の足に合わせて角度を調整することも可能です。
前述の通り、職人さんに「すげ直し」で調整してもらうことが一番確実なので、草履を購入の際には希望を伝えてすげてもらいましょう。

トピックス:草履の調整「すげる」とは
※クリックすると該当箇所に移動します
1.草履を「すげる」とは
「草履をすげる」とは、草履の台に鼻緒を取り付ける作業のことをいいます。
具体的な意味
- 草履は「台」と「鼻緒」に分かれていて、購入時や修理時に 職人が台に鼻緒を通し、結んで固定する作業 を「すげる」と言います。
- 靴ひもを結ぶような一時的なものではなく、専用の道具を使ってしっかりと固定します。
おおまかな作業の流れ
- 台の穴(前坪と左右の穴)に鼻緒を通す
- 裏側で紐を結び、木槌などで叩いて固定する
- 鼻緒の長さや高さを調整し、足に合うように仕上げる
特徴
- 鼻緒は「すげ直し」が可能で、台や鼻緒だけを交換して長く使えます。
- 新しい草履を買ったとき、鼻緒がまだ固いので、最初に自分の足に合わせて「すげてもらう」ことが大切。
- 足幅が広い・甲が高いなど、個人の足に合わせた調整ができるのも魅力です。
つまり「草履をすげる」とは、自分の足に合うように草履を仕立てる大事な工程なのです。
次に、草履をすげてもらうときに、職人さんへ伝えると仕上がりがグッと楽になる 調整のポイント をまとめました。
2.草履をすげる時に伝えるべきこと
足のサイズ感
甲の高さ
- 甲が高い → 鼻緒を少しゆるめにすげてもらう
- 甲が低い → 鼻緒をきつめにしてもらう
足幅
- 幅広 → 鼻緒を外側に倒すように調整してもらう
- 幅狭 → 鼻緒をやや内側に寄せてもらう
歩きやすさの希望
- きっちり履きたい(フォーマル・礼装)
→ 鼻緒をややきつめに。足が前に出にくく、きちんと見える。
- 楽に歩きたい(普段着・カジュアル)
→ 鼻緒を少しゆるめに。指の股が痛くなりにくく、歩行が楽。
指の股(前坪)のきつさ
- 初めは少しきつめにすげてもらうのが基本ですが、
- 足がすぐ痛くなる人 → ややゆるめ
- 長時間履く予定がある → 普通〜ややきつめ
かかとの出具合
- フォーマル:かかとが5mm程度出るようにすげてもらう
- カジュアル:1cm程度出して軽やかに
3.伝え方のコツ
「甲が高めなので少しゆるめでお願いします」
「長時間歩くので楽に履けるように」
「フォーマル用なので、見た目をきっちりと」
このように用途と足の特徴を伝えると、職人さんが調整しやすいです。
草履は鼻緒のすげ方ひとつで「痛い靴」から「一日中歩ける靴」に変わります。
しかしながら、草履はすげてもらった直後は鼻緒が固く、足に馴染むまでに時間がかかります。せっかく自分の足にピッタリの草履をすげてもらったのに、馴染む前に長時間お出かけしてしまうのはおすすめできかねます。そこでここからは、草履を履き慣らすコツ をまとめます。

4.草履を履きならすコツ
短時間ずつ履く
- いきなり長時間はNG。
- 家の中で10分〜30分くらい履いて、徐々に足を慣らす。
- 鼻緒の当たる場所が少しずつ柔らかくなり、足の形に沿って馴染みます。
指の股(前坪)を柔らかくする
- 鼻緒が硬いと指の股が痛くなりやすいので、手で軽く揉んで柔らかくしておくと◎。
- お店によっては「前坪を揉んで柔らかくしてから渡す」サービスもあります。
鼻緒を少し動かす
- 鼻緒は完全固定ではなく、少し動かせます。
- 指の股や甲が痛い場合、手で前後左右に軽く揺らして「ゆとり」を出すと楽になります。
足袋や靴下を使う
- 足袋や「足袋ソックス」を履いて慣らすと、摩擦が減って痛みを防げます。
- 夏場なら薄手の足袋カバーもおすすめ。
長時間の外出は「慣れてから」
- 新品の草履でいきなり成人式やお茶会など長時間の場に出ると、足が痛くなることも。
- 本番の前に必ず2〜3回は短時間履いて、馴染ませておくと安心です。
もし草履を履いていて痛くなったら、部分的に強く当たる場合は職人さんに再調整してもらうのが良いでしょう。
出先での応急処置 としては、鼻緒カバーの使用や絆創膏を活用してみてください。
草履は「鼻緒を育てて、自分の足に合う一足にしていく」感覚の履物ですので、コツコツ慣らして行きましょう。
5.鼻緒と台の組み合わせでもっと快適に
草履の鼻緒は 素材(布・革・組紐など)×太さ(太・細・丸ぐけ)×デザイン(無地・柄・刺繍など) の組み合わせで多彩に展開されています。
履きやすさは 台の形・高さ・鼻緒の太さや柔らかさ で大きく変わります。
一言でいえば、「低め〜中くらいの台」+「太めの柔らかい鼻緒」+「クッション性のある台」 が履きやすい草履の条件です。
特に太めの鼻緒は足の甲に食い込みにくく、安定感があって痛くなりにくい性質があるのでおすすめです。素材も丸ぐけや布地、帯地のものが柔らかく足に優しいつくりになっています。
普段着や街歩き用として草履を用意するのなら、低めの台と太い鼻緒の組み合わせがベストです。
草履をすげる際には、せっかくなので台や鼻緒の種類にもこだわりたいものですね。
以上、ご参考になりましたでしょうか?
下記、着物大辞典では歴史やTPOなども紹介していますので合わせてご参考にしてください!
→ 最新の着物の楽しみ方はこちらの記事で紹介しています

さいごに
草履のサイズ選びは洋靴と異なり、かかとが5mm〜1cm出るくらいが理想ですが、履き心地は鼻緒の調整で大きく変わるため、購入時に職人に「すげ直し」で自分の足に合わせてもらうことが大切です。
すげ直したものに関しても、新品は鼻緒が硬いため、まずは家で短時間ずつ履いて慣らすのがおすすめです。
草履は「鼻緒を育てて自分の足に合わせていく履物」であり、調整と慣らしを重ねて快適な一足に育てていきましょう。
なお、すずのきでも草履をすげることが可能です。
2025年10月23日から行われる【きもの紀行in浅草2025】では、京都の和装小物メーカー「襟の衿秀」が初出店となります。
たくさんの草履台と鼻緒の中から好きなものを選んで自分だけのオリジナル草履を作れますので、この機会をお見逃し無く!
【きもの紀行in浅草2025】についてはこちらの記事で紹介しています。↓
【お手入れ相談会】について詳しく知りたい方はこちら。↓
着付けやお手入れも安心!ご購入後のアフターフォローもばっちり

すずのきではその後の着付けのフォローや着て楽しむお出かけ会のご提案、お手入れなどのアフターケアまで、皆様の着物ライフをトータルでサポートしております。ご興味のある方はぜひ、お近くのお店までお気軽にお立ち寄りくださいませ。
すずのき・絹絵屋・たまゆうは創業から50年以上続く、関東から東北まで28店舗を構える着物・振袖専門店です。
着物をもっと楽しんでいただきたいという想いから、着物でお出かけ会、着方教室、フォトコンテストなどのお楽しみイベントを各種開催。お客様に安心いただける、地域密着の着物屋さんを目指しています。
青森、秋田、岩手、宮城、福島、栃木、茨城、千葉、神奈川、埼玉、東京での成人式の振袖選び、ママ振り、着物のお手入れや着物の着付けのご相談など、着物のことならなんでもお気軽にご相談ください。
振袖に関する情報はこちらからご覧ください。↓
振袖サイト